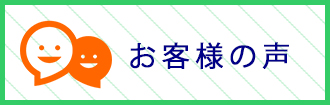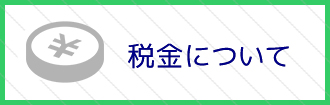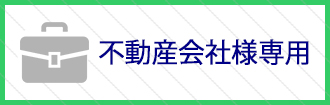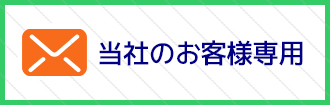築年数が古い物件=住みづらい、というイメージを持っていませんか?
実は、古い団地に魅力を感じ、あえてそこを選ぶ人が増えています。その理由のひとつが「暮らしに本当に必要なものだけを選びとる」シンプルな生活スタイル。いわゆる“ミニマリスト”たちは、古さをネガティブに捉えるのではなく、「余白」として楽しんでいるのです。
今回は、築47年の団地でミニマルな暮らしを実践している住人のキッチンから、実際に「必要だったもの」と「なくても困らなかったもの」をヒントに、快適な住まいづくりの考え方を探ってみましょう。
■ 古いキッチンでも暮らしやすい?その答えは「工夫と視点」にあった
団地のキッチンは、スペースも設備もコンパクト。最新のシステムキッチンのような便利機能はありません。けれど、“限られた中で工夫する”という視点があれば、それはむしろ暮らしをシンプルに整えるチャンスでもあります。
「便利そうだから」ではなく、「実際に使うかどうか」。モノを持つ基準を明確にすれば、キッチンは自然と整っていくのです。
■ ミニマリストが選んだ「必要なもの」3選
1. 毎日使う「鍋とフライパン」は1つずつで十分
複数サイズの調理器具を持っていた頃もあったけれど、実際に使うのはいつも同じアイテムばかり。そこで行き着いたのは、使い勝手のいい深型フライパンと、万能鍋の2つだけ。これだけあれば、炒める・煮る・茹でるが完結します。
必要以上に選択肢があると、かえって迷いが増えるもの。使い込んだ道具には愛着も生まれ、暮らしにリズムが生まれます。
2. 「見せる収納」のための吊り下げラック
収納が限られた団地のキッチンでは、壁や天井下の“縦の空間”を有効活用。吊り下げラックに鍋やキッチンツールを引っかけておけば、使いたいときにすぐ手に取れ、視覚的にもスッキリします。
これは「片付ける場所を作る」というより、「しまわずに整える」という発想。忙しい日々でも、すぐ片付けられる環境が心の余裕につながります。
3. サイズを決めた「収納ケース」
キッチン収納のポイントは、棚や引き出しを“区切る”こと。無印良品などのシンプルな収納ケースを使って、アイテムの定位置を決めると、使い終わったものをすぐ戻せるようになります。
特に、調味料や乾物、カトラリーなどの細かいものは、ケースに入れてラベリングしておくと迷いがありません。
■ 手放してよかった「必要なかったもの」
1. 食器棚や大きな収納家具
限られたスペースでは、収納そのものが場所を取ってしまうことも。キッチン用の大型収納はあえて置かず、オープンラックに必要なものだけを並べたことで、空間が広く使えるようになったとのこと。
“モノを収納するためにモノを増やす”という悪循環を断ち切ることで、動線もスムーズに。
2. 大量の食器や調理器具
来客を想定して複数セット揃えていた食器も、実際に一人で使う分には2~3セットで十分。使っていないモノを手放すと、気持ちもスペースも軽くなります。
「必要になったら、そのとき考える」。この考え方が、身の丈に合ったキッチンを作る基本です。
■ 団地だからこそ実現できた、余白を楽しむ暮らし
古い団地の良さは、過剰に作り込まれていない「余白」にあります。必要最低限の設備だからこそ、自分の暮らしに合わせて自由にカスタマイズしやすいのです。
たとえば、タイル張りの壁にお気に入りのフックを取り付けたり、天板に板を乗せて作業スペースを広げたり──。団地のキッチンは、住む人のアイデア次第でいくらでも快適に変えていくことができるのです。
■ まとめ:キッチンは“豊かさ”の指標になる
キッチンのあり方は、その人の暮らし方や価値観がよく表れる場所です。便利さや見た目の華やかさよりも、「ちゃんと自分に合っているかどうか」。この視点で選び取ったアイテムや空間こそが、暮らしを支える名脇役になっていきます。
築年数が経過した物件でも、住まいは自分らしく整えられる。団地という空間をきっかけに、自分にとっての“本当に必要な暮らし”を見つけてみませんか?

 お気に入り
お気に入り